毎年の健康診断や学校検診、
人間ドックの心電図結果で
異常Q波と記載されていると、
不安になる方は少なくありません。
「何が原因?」
「心筋梗塞とかの可能性があるの?」
「症状がなければ問題ない?」
──と心配になりますよね。
この記事では
循環器専門の医師が、
- 異常Q波とは何か
- どんな原因や病気の可能性があるか
- 健康診断後はどうしたらいいのか
について、わかりやすく解説いたします。
※本記事は診断や治療を目的としたものではありません。
※受診の判断材料や、理解を深める参考としてお使いください。
※検査元から受診指示がある方は、必ず医療機関をご受診ください。
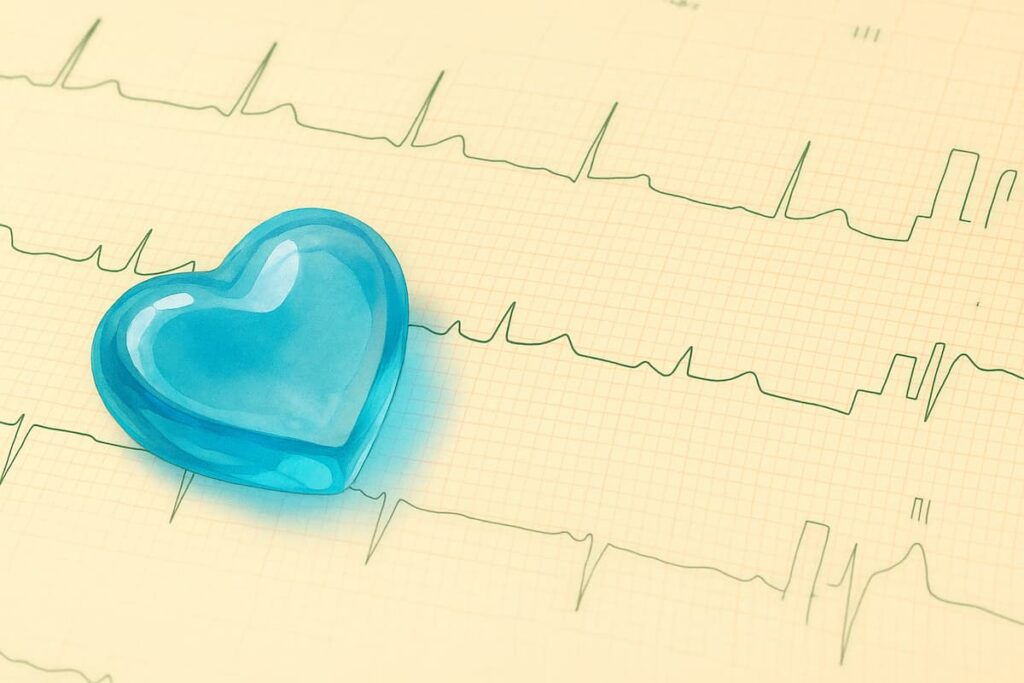
📌本記事は、下記の親ページの続編として執筆しています。
心電図で異常を指摘された方は
まずはこちらの記事から順にご覧いただくと、
より理解が深まります。
異常Q波の心電図と自覚症状
心電図で異常Q波が見られるときに、
あらわれることがある症状には
次のようなものがあります:
- 胸の痛みや圧迫感
- 息切れ(とくに動いたとき)
- 動悸(ドキドキする感じ)
- 冷や汗
- 吐き気やめまい
- 体のだるさや疲れやすさ
一方で、健康な方でも
異常Q波が出ることがあり、
その場合はまったく自覚症状がないこともあります。
つまり、「心電図に異常Q波がある」からといって、
必ず症状が出るとは限りません。
異常Q波の背景や原因によって、
自覚症状の有無や現れ方はさまざまです。
たとえば、心筋梗塞のあとや
心筋症による心不全などがあると、
症状を伴うケースが多くなります。
ただし、こうした病気が
自覚のないまま進行していることもあるため、
注意が必要です。
もしも心電図で「異常Q波がある」
と言われたときに、
上記のような自覚症状があった
あるいは現在も気になる体調の変化がある場合は
循環器内科や循環器科の
専門医への相談をおすすめします。
早めのチェックが、将来の安心につながります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
✅健康診断の心電図で【経過観察】や【異常なし】…でも体調不良? それって病気?
心電図の波形異常、異常Q波で考えられる原因や病気など
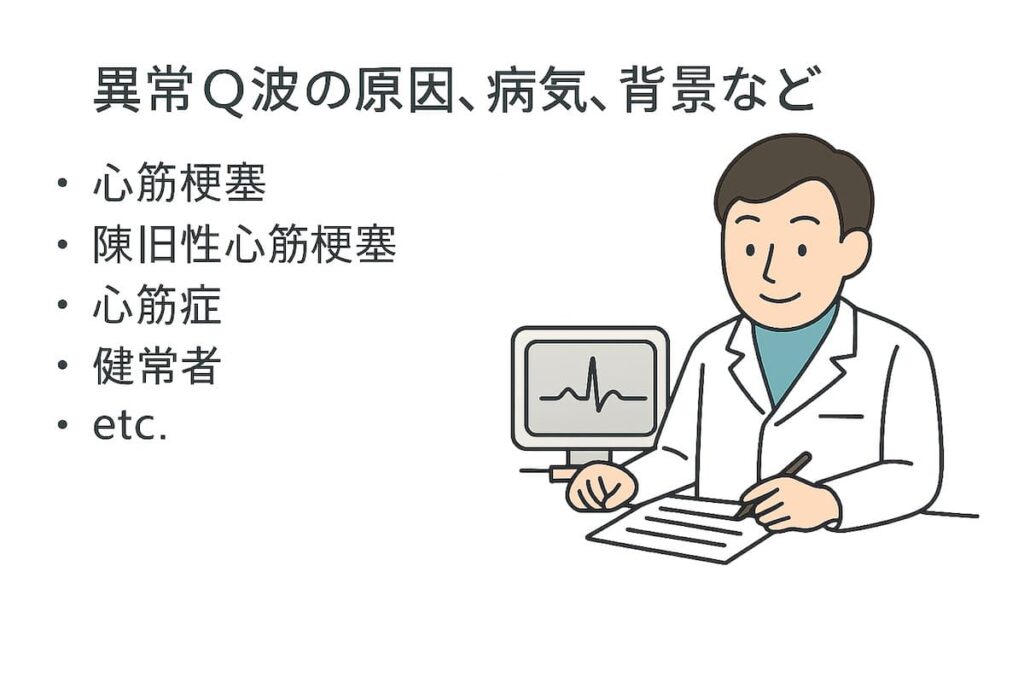
・心筋梗塞
冠動脈という心臓の栄養血管が、
閉塞したり、狭くなる病気です。
心不全や、突然死の原因となります。
心電図検査にて、
異常Q波が確認される事があります。
・陳旧性心筋梗塞
過去に心筋梗塞を起こしたことがある方は、
心電図検査にて
異常Q波が確認される事があります。
・心筋症
心臓は主に筋肉で構成されており、
ポンプの役割を担っています。
心臓の筋肉異常が生じる病気です。
左心室の筋肉が薄くなり
収縮能が低下する拡張型心筋症、
一部または全部が分厚くなる
肥大型心筋症などが知られています。
心不全や、突然死の原因となります。
心電図上、異常Q波が出現する場合があります。
・健常者
特に基礎疾患(含心臓疾患)を有さない方にも、
心電図所見 異常Q波を認める事があります。
心電図の異常Q波とは?|ザックリ解説
心臓が1回拍動すると、
その電気の流れにあわせた
ギザギザした波が心電図に記録されます。
それらのギザギザは各所に名称があります。
異常Q波は、心電図でQ波という部分が
通常より深く・幅広く出ている状態を指します。
これは、過去に心筋の一部が
ダメージを受けた可能性があることを示すサインで、
特に心筋梗塞の痕跡として現れることもあります。
自覚症状がないまま
見つかることもありますが、
胸の痛みや息切れなどがあった方は注意が必要です。
異常Q波の心電図|受診前のチェックポイントは?
健康診断や学校検診で
異常Q波を指摘され、
気になる症状や
ご不安がある場合には、
循環器内科(循環器科)を標榜する
クリニックや病院の受診が推奨されます。
クリニックや病院の公式サイトには、
医師のプロフィールが掲載されていることが多く、
受診前に、
以下のような記載があるかを
チェックしてみましょう:
- ○○心血管インターベンション治療学会:専門医/認定医/所属
→ カテーテル治療(ステントなど)などを専門とする医師 - ◇◇循環器学会:専門医/認定医/所属
→ 心臓病全般を専門とする医師 - △△心臓病学会:専門医/認定医/所属
→ 心臓疾患に精通した医師
専門性をもっている
医師の診察を受けることで、
スムーズな診断や検査の進行が期待できます。
必要に応じて、
より高度な医療機器を備えた
総合病院や専門病院などへの紹介も
手早く調整してもらえる可能性が高くなります。
可能であれば、
希望する医師の診察日や
予約の可否を事前に電話で
確認しておくと安心です。
とくに専門外来は
診療日が限られている場合もあるため、
事前確認で無駄な待ち時間や
再訪の手間を減らせるかもしれません。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図の異常Q波|受診後の流れはどうなるの?
毎年の健康診断や学校検診で
「心電図:異常Q波」の結果をみて、
「これから具体的にどうしたらいい?」
と考えますよね。
まずは、循環器内科・循環器科を縹渺する
お近くのクリニックや医院への受診をご検討ください。
受診後の流れについて
医師の診察のうえで、「異常Q波」の心電図が
- 本当に心配すべき異常か
- あるいは経過観察だけでいいものか
といった判断のため、
外来で出来る追加検査の計画が
当日~2週間程度以内で
予定されるのが一般的です。
※具体的な検査については、後のセクションで詳しく解説いたします。
検査結果が出た後の主なパターン
検査結果が揃うと、
医師の診察結果とあわせて
今後の方針が決まります。
とはいえ、心電図異常=すぐ治療が必要というケースは少数で、
多くの場合「経過観察」となります。
1. 経過観察となるケース
軽いもの:
「特に心配ありませんね。
気になる症状などがあれば、またご来院ください。」
念のため:
「○ヵ月後に再度ご来院いただき、
もう一度検査をしましょう。」
頓服の相談:
「強い症状などが出た時に備えて、
必要に応じてお薬を持っておきましょう。」
2. お薬による治療が始まるケース
心臓の負担を軽くしたり、
脈の調子を整えるなどのために
医師の判断によりお薬が処方され
定期通院が開始となることもあります。
3. 大きな病院への紹介となるケース
より精密な検査や治療が必要と
判断された場合には、
急性期総合病院、大学病院、
専門病院などへの紹介受診することになります。
緊急対応が必要なケース(まれ)
危険性が高い不整脈や
緊急性のある心疾患が疑われる場合は、
当日中の受診を指示され、
直ちに紹介状が発行されることがあります。
※救急搬送となるケースもあります。
紹介予約による検査~治療
より高度な検査や治療
(CT・シンチグラフィ・MRI・心臓カテーテルなど)
が必要な場合には、
紹介受診の予約が手配されます。
もちろん、最初から大きな病院を
受診しても構いませんが、
効率的でない可能性もあります。
- 専門外来の予約が取りずらい
- 紹介状がないと費用が多くかかる
- 待ち時間が長くなる
総合病院などの大きな病院では、
上記のような可能性があります。
一方で、地域のクリニックや医院では
比較的早く受診することが可能で、
「病診連携」と呼ばれる、
必要に応じて大きな病院への紹介状を
書いてもらえる仕組みがあります。
まずはお近くの医療機関に相談し、
必要に応じて大きな病院などへ
紹介してもらう流れの方が、
スムーズな場合が多いです。
自己判断せず、専門科の診断を
心電図の異常と聞くと
つい「重い病気かも…」
とご不安になってしまうかもしれません。
実際には「検査したら特に問題なかった」
というケースが多数です。
しかし、心臓は命に直結する
重要臓器の一つであることは確かです。
「念のため」でも、
専門医などの診察や検査を
積極的に受けることをお勧めいたします。
心配を一人で抱えこまず、
ご自身の心臓の状態を知ることが
安心につながります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図検査の異常Q波で、実施されることのある外来精密検査
- 安静心電図検査
- 胸部レントゲン検査
- 心臓超音波検査
- 冠動脈造影CT検査
- 運動負荷心電図検査
- 血液検査
- 【入院】心臓カテーテル検査
- その他
上記の検査は、
目的が重複しているものもあり、
全てを行う必要があるわけではありません。
症状の有無、年齢、生活習慣、
基礎疾患(高血圧・糖尿病など)、
過去の病歴などをふまえて、
医師の判断で適切な検査が選択されます。
特に、胸痛や動悸などの症状がある場合や、
リスク因子が重なっている場合は、
より詳しい検査が提案されることがあります。
安静心電図検査
- 所要時間: 1分程度
- 自己負担額: 約130円 ~ 400円(自己負担割合によります)
「健診で心電図やったのに、またやるの?」
と思う方もみえるかもしれません。
前回の心電図との比較や再現性の確認のために
再度行うことがあります。
タイミングが違えば
波形も変化することがあるからです。
多くの医療機関では、
検査当日に結果の説明が可能です。
胸部レントゲン検査
• 所要時間:約5分
• 自己負担額:約150円〜500円
胸部のX線撮影によって
心臓の大きさや形、肺の状態などを確認できます。
簡便で広く行われている検査で、
心不全の有無や肺の病気の除外にも役立ちます。
結果説明は当日中が一般的です。
心臓超音波検査
- 所要時間: 20~30分程度
- 自己負担額: 約880円 ~ 2,800円(自己負担割合によります)
テレビ番組などで、
妊婦さんがお腹の赤ちゃんを
超音波で見ているシーンを
見たことはありませんか?
心臓超音波検査も
まったく同じ仕組みの検査です。
左胸に小さな機器(プローブ)をあてて、
心臓の動きや筋肉の厚み、
弁の働き、血流の流れなどを、
映像としてリアルタイムに観察できます。
痛みもなく、体に害もない安全な検査で、
当日中に結果を聞けるケースも多いです。
冠動脈造影CT検査
- 所要時間: 20分程度
- 自己負担額: 約3,000円 ~ 9,200円(自己負担割合によります)
冠動脈とは、
心臓に栄養を送る大切な血管のこと。
この血管が詰まっていないか・狭くなっていないか
を調べるための検査が
「冠動脈造影CT検査」です。
造影剤という薬剤を
点滴で注入しながらCT撮影を行い、
血管の状態を画像で詳細に確認します。
ただし、腎機能が低下している方や、
呼吸を30秒ほど止めるのが難しい方には行えないことがあります。
CT撮影そのものは20分程度ですが、
点滴や解析などを含めて
全体で3時間程度かかることもあります。
運動負荷心電図検査
運動をすることで
心臓に軽いストレス(負荷)をかけて、
心電図の変化や不整脈の出現を
観察する検査です。
ルームランナーを使って歩いたり、
エアロバイクをこいだり
踏み台昇降を行ったりしながら心電図を測定します。
当日に結果説明が可能なことが多いです。
血液検査
- 所要時間: 3分程度
- 自己負担額: 約1,200円 ~ 3,600円(自己負担割合によります)
採血をして、心臓の負担や異常の可能性、
関連する内科的要因をチェックします。
たとえば、貧血による動悸、
電解質異常や甲状腺機能異常による不整脈なども、
この検査で確認できます。
また、心筋にかかる負担を数値で示すマーカー(BNPなど)も、
診断の参考になります。
結果は当日〜1週間以内にわかることが多いです。
【入院】心臓カテーテル検査
症状や他の検査結果から
必要と判断された場合、
最初から心臓カテーテル検査が
提案されることもあります。
この検査は、多くの医療機関で
入院による実施となります。
心臓の血管(冠動脈)をより精密に評価するため
カテーテルと呼ばれる細い管を動脈から挿入し、
造影剤を注入して直接検査します。
挿入部位は手首・肘・足のいずれかで、
局所麻酔を使用します。
より正確な診断・治療方針の決定に役立つ検査です。
補足:
- 上記の所要時間は検査自体の目安であり、説明や待ち時間は含みません。
- 費用は検査部分のみの自己負担額の目安です(診察・処方等は別途)。
- 実施可能な検査は、医療機関の設備や体制により異なります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
スマートウォッチ心電図で異常Q波はわかる?
スマートウォッチ心電図で
記録できるのは脈が
「不規則かどうか」、「速いか遅いか」
といった不整脈の一部に限られます。
そのため、異常Q波のような波形異常を
スマートウォッチで判定することはできません。
異常Q波の確認には
必ず病院やクリニックで行う12誘導心電図が必要です。
スマートウォッチはあくまで
「不整脈のチェック」に役立つツールと考え、
波形異常の確認には
医療機関の検査を受けましょう。
※執筆時点での情報をもとにしています。
※スマートウォッチの機能や医療機器認定は日々アップデートされていますので、
最新情報はメーカーや公式発表をご確認ください。
心電図、異常Q波の定義・基準など
ここからは、少し難しい話かもしれません。
ご興味のある方は読み進めて下さいね。
心電図検査の異常Q波は、心電図波形の異常となります。
正常でも、心室中隔の脱分極を反映した、
幅の狭い小さなQ波を認めます。
多くはⅠ, aVL, V5, V6誘導でみられます。
Q波が、Q波幅 ≧ 0.04秒(1.0mm)、
またはQ波の深さがR波高の1/4以上の時、
異常Q波とされます。
判断時の注意点としては、
通常aVR誘導はQS型またはQr型のQRS波形を示すため、
幅の広いQ波は正常とされます。
Ⅲ誘導も、健常な方でQS型
またはQr型波形を示すことが多く、
ⅡまたはaVF誘導に異常が無ければ
異常Q波とはされません。
aVL誘導は、健常な方でも小さなQ波を認め、
Q波の深さがR波高の1/2以上の時のみ
異常Q波とされます。
心筋梗塞が、異常Q波を示すことはよく知られています。
心筋梗塞の診断だけでなく、
心筋梗塞領域(範囲)の推定にも利用されます。
しかし、心筋梗塞以外の疾患にもみられ、
肥大型心筋症は異常Q波を時々示します。
異常Q波に関しては、以上となります。
📙医療関係者むけ、お勧め書籍|Amazonで見る
ここまで読んでいただき、
ありがとうございます!
