健康診断、学校検診などの心電図検査で、
- 「心電図異常を言われたけど、どうすればいいの…?」
- 「心電図の異常波形とか、不整脈って書いてあったけど、これってなに?」
- 「これって、何科に受診したらいいの?」
──そんなふうに、心電図異常を言われて、不安や疑問を抱えていませんか?

健康診断や学校検診などで受ける検査は、
スクリーニング検査といって、
病気があるかもしれないサインを、
早めに見つけるためのものです。
そのため、「心電図に異常があります」と言われても、
すぐに重い病気と決まるわけではありません。
ただし、所見の内容や症状の有無によっては、
ちゃんと調べた方が安心です。
もし不安なときは、次のステップをおすすめします:
- 近くのクリニックや病院を受診する
- 医師の診察を受ける
- 必要に応じて、外来で詳しい検査をする
放っておいていいものもありますが、
中には早めの対応が必要な種類もあります。
気になることがあれば、早めに相談してみましょう。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
このサイトについて|自己紹介
こんにちは。
循環器専門医として20年以上、
心筋梗塞や狭心症、不整脈など、
たくさんの心臓病を診てきました。
今は地域の病院で、
訪問診療や健診の読影などを担当しています。
「心電図に異常があると言われて不安です…」という声も多く、
少しでも安心につながればと思い、
このブログを書いています。
専門的な内容をできるだけやさしく、
噛み砕いてお届けいたします。
※ブログ内の全ての記事は医療広告ガイドラインを遵守していますが、診断や治療を目的としたものではありません。
※受診の判断材料や、理解を深める参考としてお使いください。
※検査元から受診指示がある方は、必ず医療機関をご受診ください。
心電図の異常を指摘され
生命保険・医療保険に不安がある方は、
下記ページをご覧ください。
心電図に異常があったら、まずはクリニックや病院の受診を検討しましょう
その際は、
「何科があるか(標榜科)」、
「どんな専門をもっているか」、
をチェックしてから行くことを検討してください。
そのクリニックが、
どんな分野を得意としているかがわかります。
たいていの場合、クリニックの公式ホームページに、
標榜科や専門科の情報が載っています。
ホームページがない場合でも、
看板に掲示されていることが多いので、
参考にしてみてください。
また、診察の予約が必要かどうかも事前に確認すると安心です。
電話で聞いておけば、当日の流れがスムーズになりますよ。
心電図に異常が出たとき、何科を受診?
受診する前に、
そのクリニックが「循環器内科」または「循環器科」
を標榜しているかどうかの確認をお勧めします。
健康診断や学校検診での 心電図は、
「スクリーニング検査(病気の可能性を探るための検査)」です。
症状がある方や、不安が残る方は、
次のステップとして医師による診察や、
外来での精密検査を受けることがすすめられます。
なぜ「循環器内科」や「循環器科」なのか?
- 心電図異常の原因は、**心臓に関する病気(心筋梗塞、狭心症、不整脈、心筋症など)**であることが多いため
- 循環器専門医が在籍している確率が高く、追加検査の判断や治療に慣れていることが多い
- 心臓の検査に必要な設備が整っている可能性が高い
- 「ハートセンター」や「ハートクリニック」という名前の医療機関も、心臓を専門にしていることを期待できます。
もちろん、どんなクリニックでも、
すべての検査・治療が完結するわけではありませんが、
初期対応や精密検査の入口として、
循環器専門の医療機関を選ぶことを検討されてください。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図で見られる異常波形・不整脈の一覧
健康診断や学校検診などで見つかる心電図の「異常波形」や「不整脈」について、
それぞれの種類、対応方法や、考えられる病気・原因などを、
以下のリンク先で詳しく解説しています。
気になる所見名をクリックして、ご覧ください。
👉50音・ABC順に並んでいます
- 異常Q波(いじょうきゅうは)
- 異常なし(いじょうなし)
- 異所性心房調律(いしょせいしんぼうちょうりつ)
- Ⅰ度房室ブロック(いちどぼうしつぶろっく)
- 陰性T波(いんせいてぃは)
- 右軸偏位(うじくへんい)
- 右室高電位(うしつこうでんい)
- 右室肥大(うしつひだい)
- 右房拡大(うぼうかくだい)
- 右房負荷(うぼうふか)
- 完全右脚ブロック(かんぜんうきゃくぶろっく)
- 完全左脚ブロック(かんぜんさきゃくぶろっく)
- 完全房室ブロック(かんぜんぼうしつぶろっく)
- 高度房室ブロック(こうどぼうしつぶろっく)
- 左脚後枝ブロック(さきゃくこうしぶろっく)
- 左脚前枝ブロック(さきゃくぜんしぶろっく)
- 左軸偏位(さじくへんい)
- 左室高電位(さしつこうでんい)
- 左室肥大(さしつひだい)
- 左房拡大(さぼうかくだい)
- 左房負荷(さぼうふか)
- 上室性期外収縮(じょうしつせいきがいしゅうしゅく)
- 心室性期外収縮(しんしつせいきがいしゅうしゅく)
- 心室内伝導障害(しんしつないでんどうしょうがい)
- 心房細動(しんぼうさいどう)
- 心房粗動(しんぼうそどう)
- 低電位差(ていでんいさ)
- 洞徐脈(どうじょみゃく)
- 洞性不整脈(どうせいふせいみゃく)
- 洞頻脈(どうひんみゃく)
- 洞性徐脈(どうせいじょみゃく)
- 洞性頻脈(どうせいひんみゃく)
- 洞不整脈(どうふせいみゃく)
- 時計回転(とけいかいてん)
- Ⅱ度房室ブロック(Mobitz)(にどぼうしつぶろっく もびっつ)
- Ⅱ度房室ブロック(Wenckebach)(にどぼうしつぶろっく うぇんけばっは)
- Ⅱ度房室ブロック(2:1)(にどぼうしつぶろっく にたいいち)
- 判定不能(はんていふのう)
- 反時計回転(はんとけいかいてん)
- 不完全右脚ブロック(ふかんぜんうきゃくぶろっく)
- 不完全左脚ブロック(ふかんぜんさきゃくぶろっく)
- 平低T波(へいていてぃは)
- 房室接合部調律(ぼうしつせつごうぶちょうりつ)
- Brugada(ブルガダ)型心電図(ぶるがだがたしんでんず)
- PR延長(ぴーあーるえんちょう)
- PQ延長(ぴーきゅーえんちょう)
- QT延長(きゅうてぃえんちょう)
- R波の増高不良(あーるはのぞうこうふりょう)
- RSR’パターン(あーるえすあーるぱたーん)
- ST上昇(えすてぃじょうしょう)
- ST-T異常(えすてぃてぃいじょう)
- ST低下(えすてぃていか)
- T波増高(てぃはぞうこう)
- WPW症候群(だぶりゅうぴぃだぶりゅうしょうこうぐん)
※この一覧は、すべての心電図所見を網羅しているわけではありません。
※記載のない所見でも、内容によってはクリニックや病院の受診が必要となる場合があります。
※ご不安なことがあれば、早めに医療機関でご相談ください。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
✅健康診断の心電図で【経過観察】や【異常なし】…でも体調不良? それって病気?
心電図の成り立ち ~ 正常・異常について
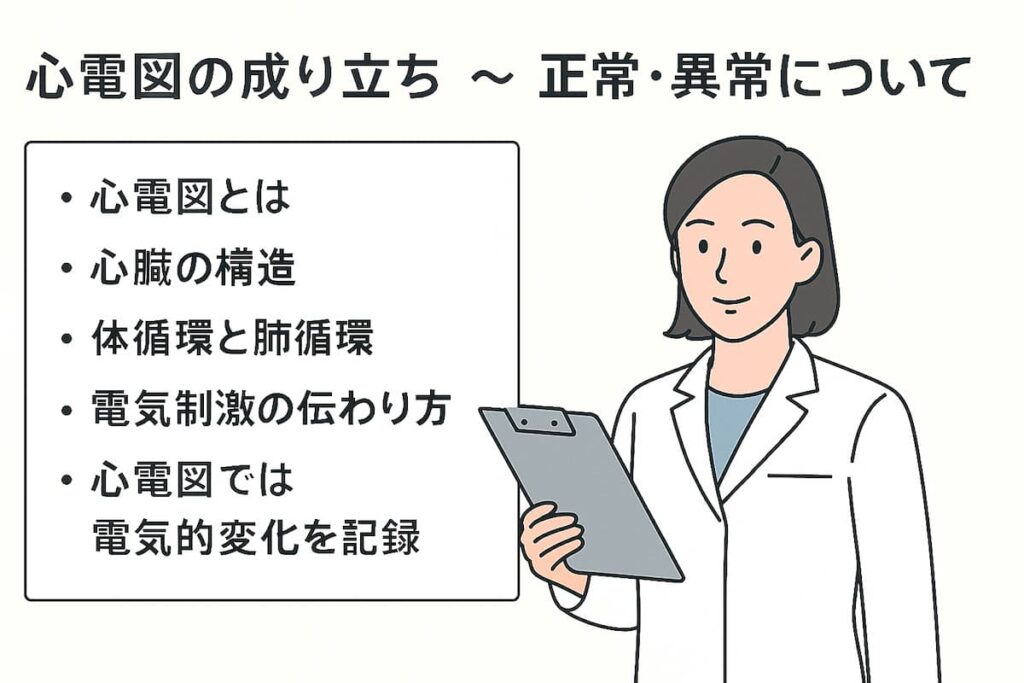
心電図とは
心臓はポンプとして、
1日の間に、約10万回
収縮と拡張を繰り返し、
血液を全身に送り出しています。
約4Lから8Lの血液量を、
1分間に送り出していて、
1日でに送り出す血液量は、
実に約8トンにもなります。
1回の収縮と拡張は
まず電気的な刺激が心臓に起こり、
それをトリガーとして、電気的な興奮が伝播し
心臓の筋肉が収縮します。
電気的な興奮がおさまると拡張します。
この過程を、ずっと繰り返します。
電気的な刺激の起こり方によって、
心臓の収縮と拡張のタイミングは変わります。
心電図では心臓の
電気的な刺激~興奮の伝播~おさまるまでの過程を記録します。
心臓の機能や構造から、
心電図の描かれ方まで、解説します。
心臓の構造
心臓には上の方に位置する心房と、
下の方に位置する心室があります。
心房と心室は、
右心房と左心房、
右心室と左心室と
それぞれさらに左右2つに分かれています。
右心房と左心房の間に、心房中隔があり
右心室と左心室の間に、心室中隔があります。
三尖弁は右心房出口と、右心室の入り口の間に、
僧帽弁は左心房の出口と、左心室の入り口の間に位置しています。
大動脈弁は左心室の出口と、大動脈の入り口の間に、
肺動脈弁は右心房の入り口と、肺動脈の出口に位置しています。
体循環と肺循環
血液は、
左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房→左心室
の順で循環しています。
左心室の収縮により、大動脈をとおって
全身に送られた血液は
各臓器や組織において、酸素が消費され静脈血となります。
静脈血は大静脈をとおして、
右心房に送り込まれます。
この循環過程の事を、体循環と呼びます。
右心房に送り込まれた、
酸素が消費されている静脈血は、
右心室から肺動脈をとおして
肺に送られます。
肺で、呼吸によって酸素をたくさん含んだ動脈血となり、
肺静脈をとおして、左心房に戻ってきます。
こちらの循環過程は、肺循環と呼ばれます。
心臓に、特に問題が無ければ心室の拡張時に、
僧帽弁、三尖弁は開放され、
心室の拡張が終わる頃に、心房は収縮します。
心室が収縮する際は、
血液が心室から心房に逆流してしまわないように
僧帽弁と三尖弁は閉鎖され、心房が拡張します。
こういった心房、
心室の収縮と拡張のタイミングは
電気的刺激と興奮の伝播によって
上手に調節されています。
電気刺激の伝わり方
心臓が動くトリガーとなる
電気的な刺激は、
右心房内の洞結節と呼ばれる
細胞の塊から自動的に発生します。
その刺激が、右心房から左心房に
電気的興奮として伝播し、
心房全体が興奮して心房収縮が起こります。
さらに心房の興奮は、
房室結節と呼ばれるところに伝わり
ヒス束を通って、右心室側にある右脚、
左心室側にある左脚からプルキンエ線維に伝播し、
心室収縮が生じます。
そのころには、
心房の興奮はおさまる過程に入っています。
洞結節→心房→房室結節→ヒス束→脚(左脚と右脚)→プルキンエ線維→心室筋
という電気興奮の一連の伝播過程は
刺激伝導系と呼ばれています。
心臓は電気刺激を自動的に発生し、
心房から心室に電気的興奮を伝導し
心房筋、心室筋を興奮、収縮させ、
さらには興奮がおさまることで拡張する機能を有しています。
これらは心臓の生理学的特徴として、
自動性、伝導性、興奮性、収縮性、拡張性と呼ばれます。
心電図は、これらのうちの収縮性、拡張性を除いた、
自動性、伝導性、興奮性を解析する検査となります。
収縮性、拡張性といった、
機械的なポンプの能力を心電図では調べることはできません。
心電図は、心臓の電気的現象を主として把握する事で、
変化から様々な病的状態を知ることが可能となります。
心電図では、電気的変化を記録します。
心臓の電気的興奮は、体表面にも影響を及ぼし、電場を生じさせます。
心臓の電気的興奮の伝播、消退により、電位(電気的な大きさ)の変化が起こります。
この電位の、体表面での大きさはmV(ミリボルト)単位の、
ごく小さなものであり、時間とともに変化します。
小さな電位を増幅させて、時間的な変化を分析するために、記録する検査機器が心電計となります。
心電計により、縦軸にmV(電位差)、横軸に秒(時間)を座標として、
心臓の電気的興奮、伝播、消退を表現したものが、心電図の波形ということになります。
後に詳しく記載しますが、心電図の波形はP波、QRS波、T波、U波により成立しています。
心房の興奮がP波、心室の興奮がQRS波、心室の興奮消退がT波で表されています。
T波の後に、成因が明確ではないU波がみられます。
📙医療関係者むけ、お勧め書籍|Amazonで見る
心電図でわかる異常について
心臓の電気刺激を最初に発する、洞結節の機能や働き、
電気興奮を伝播する刺激伝導路の状況、電気興奮が伝わると作動する心筋の興奮状態、
などに異常が生じると、心電図も変化します。
電気刺激の発生が、不規則になったり、伝播に時間がかかったり、
途中で伝わらなくなってしまったり、心房や心室の興奮に、異常が起きる事があります。
それぞれの異常に対して、結果として、心電図波形の変化が生じるため、
問題部分を分析することが出来ます。
- 電気興奮伝導の異常、不整脈
- 心臓興奮の異常からわかること
- 心電図でわかる病気など
- 心電図の記録
- 心電図記録のポイント(異常発見は正確な記録から)
- 心電図波形の構成~異常を捉えるために~
電気興奮伝導の異常、不整脈
電気的興奮が乱れ、それにより心臓の拍動が不整になると、不整脈と呼ばれます。
不整脈の種類は、多岐に渡りますが、心電図により、その原因や、種類を知ることができます。
心房や心室といった構造の、内腔拡張が起きたり、壁が分厚くなったりすると、
心房の興奮を表すP波や、心室の興奮を表すQRS波に変化が起きます。
心電図により、それらの現象を、診断することが可能となります。
心室内の伝導異常が起きると、心室全体が興奮するのに、時間がかかるようになるため、
QRS波の幅が広くなったり、QRS波の形が変わったりします。
心室内伝導路である、右脚や左脚に電気伝導のおくれや、中断が生じると、
各々、右脚ブロックや左脚ブロックと呼ばれる、心電図波形を示すようになります。
心臓興奮の異常からわかること
心筋の血流(酸素)不足、障害、炎症、代謝異常など、
何かしらの原因で、心筋興奮に異常が起きます。
すると、QRS波とT波の間、ST部分が基線より、上昇もしくは低下したり、
T波が陰性化(下向きになること)したりする事があります。
狭心症や心筋梗塞など虚血性心疾患では、ST部分の変化や、T波の変化がよくみられます。
心筋梗塞では、異常Q波と呼ばれる、特徴的な所見がQRS波に出現します。
心臓の表面を覆う、心膜という構造があります。
そこに心膜炎という炎症が起きると、心電図の基線より、ST部分が上昇する所見を認めます。
心房の電気的興奮は、通常、房室結節からヒス束を通り、心室に伝わります。
ヒス束以外に、心房と心室を連絡する、電気の通路を有する方が(WPW症候群)、ときにみえ、
WPW症候群に特有の、心電図波形を示します。
心臓自体に異常がない場合でも、カリウムやカルシウムなどの電解質異常といった、
心筋の興奮や消退に、変化をもたらす条件となると、心電図変化がおきる事があります。
心電図でわかる病気など
- 不整脈診断や、その解析
- 右心房、左心房の拡大
- 右心室、左心室の肥大、拡大
- 心室内伝導路の異常
- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)
- 心筋疾患(肥大型心筋症、拡張型心筋症など)
- 心膜炎
- Wolff-Parkinson-White(WPW)症候群
- QT延長症候群
- Brugada症候群
- 電解質異常
- etc.
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図の記録
心電図は、あお向けに寝転んで、安静にした状態で行います。
心臓から発生した数mVの電位変化を、体の表面に装着した電極で捕捉し、
心電計を用いて波形として描きます。
心電図の測定方法は、12パターンあり、12誘導心電図と呼ばれます。
心電図 四肢誘導
手足の先から、心臓の電位変化を波形として捕捉します。
両手首、左の足首に電極を装着します。
大まかな心臓の電位変化を、評価することが可能です。
心電図、四肢誘導には:
- 第Ⅰ誘導(右手首-左手首)
- 第Ⅱ誘導(右手首-左足首)
- 第Ⅲ誘導(左手首-左足首)
これらを標準肢誘導と呼びます。
また、
- aVR
- aVL
- aVF
これらは単極肢誘導と呼ばれます。
つまり手足から記録する心電図には、6パターンの方法があります。
心電図 胸部誘導
6個の電極を、右第4肋間から左5肋間あたりにかけて装着し、
四肢誘導より心臓に近い体の表面で、心臓の電位変化を心電図として捕捉します。
胸から記録する心電図にもV1, V2, V3, V4, V5, V6, と6パターンの方法があり、
より詳しく心臓の電位変化を評価する事が出来ます。
心電図の実際
- 痛みや、電気のしびれなど、全くない検査です。
- 数分間、あお向けに横になるだけで、すぐに終わります。
- リラックスすることが、良好な心電図波形をとるために必要です。
- あお向けになる時、両足を軽く開くと、体の力を抜きやすくなります
- 緊張すると、心電図に筋肉の電気成分が、混入することがあります
心電図記録のポイント(異常発見は正確な記録から)
正しい電極装着部位で、雑音がなく、基線が安定している心電図を記録することが大切です。
正しい位置に電極を装着しましょう
胸部誘導に関しては、電極の装着部位が大切です。
肋間がずれると、記録される心電図波形が大きく異なってしまう事もあります。
四肢電極の装着部位に関しては、腕の付け根~手首、足の付け根~足首の間であれば、
波形に大きな変化はないと考えられています。
手首、足首に電極を装着できない場合、位置を変えて記録しましょう。
心電図検査、電極装着方法のポイント
- アルコールで、電極装着位置の脂肪分を拭き取りましょう
- ペーストを、電極装着位置に塗り込みましょう。近くの電極装着位置のペーストと、ひとつながりにならない様に、注意が必要です。
- ペーストを、電極と皮膚の接触面に薄く塗りましょう
- 胸部の電極は、ゴム球を指でつまみ、装着位置に吸着させます。近くの電極と接触しない様に、注意が必要です。
- 四肢の電極は、両手、両足の皮膚の柔らかい位置に装着しましょう。接触面を貼り合わせるように、はさみ式の電極ではさみましょう。
心電図機械の使用方法
・機械の使用方法は、添付されている説明書をよく読みましょう。
心電図波形の構成~異常を捉えるために~
心臓が1回動いた時の心電図は、P波、QRS波、T波、(時にU波)で成り立っています。
QRS波はQ, R, Sの3要素で形成されています。
P波
心房の、電気的興奮過程を示すのがP波となります。
常では、右心房の興奮に引き続いて、左心房が興奮します。
右心房の電気的興奮の始まりが、P波の開始点となります。
開始点から2/3が右心房の興奮、後ろ2/3が左心房の興奮を示していて、
右心房と左心房、両方の興奮が融合したものが、P波となります。
陽性は上向きの振れ、陰性は下向きの振れと呼びます。
上向きに最初に振れ、その後下向きに振れる、または下向きに最初振れ、
その後に上向きに振れるものは二相性と呼ばれます。
その他、二峰性P波、尖鋭P波、平低P波などがあり、
一般的には、第Ⅱ誘導で、高さ・幅を計測します。
QRS波
右心室、左心室の筋肉の興奮を示す部分となり、
Q波の開始点から、S波の終点までをQRS波と呼びます。
QRS波の幅をQRS間隔といいます。QRS波のなかで、最初の下向きの波をQ波、
次の上向きの波をR波、その後の下向きの波をS波と呼びます。
正常な場合では、心室中隔の左心室側から、心筋の電気的興奮は開始し、
心室中隔の右心室側、右心室、左心室、心尖部、最後に心基部に向かいます。
疾患によったり、誘導により、様々な形状を示すのがQRS波です。
QRS幅の拡大は、心室に伝わる電位的興奮が、正常よりゆっくりとなり遅延している事を示します。
QRS波表現の取り決め
- 振幅の小さい時は小文字で示す(q, r, s)
- QRS波、1波内に、同じ呼称の波形を、2つ以上認める際、2番目に現れた波形に「 ‘ 」を付ける
T波
QRS波の少し後に起きるのがT波となります。
ゆるやかな勾配の曲線により、描かれます。
心室筋の電気的興奮が、収まっていく過程を示しています。
陽性、陰性、平坦など、極性と大きさに着目しましょう。
T波における平低とは、QRS波の振れ幅との相対的評価となります。
具体的にはQRS波の振幅、1/10以下を平低T波とよびます。
U波
T波に続く、小さな波を認めることがあります。
成因が今のところ、明確ではありません。
陽性波形、陰性波形、二相性波形かどうかと、大きさをチェックします。
PQ間隔
P波の始まり~QRS波の始まりまでを、PQ間隔とよびます。
心房の電気的興奮の開始から、房室接合部を伝播して、
心室筋の興奮が開始するまでの時間となります。
QRS波がR波で始まる場合は、R波までとなり、PR間隔となります。
ST部分
QRS波の終わり~T波までをST部分とよびます。
QT間隔
Q波の開始点から、T波の終了点までをQT間隔といいます。
心室筋の興奮の始まりから、消退までの時間を示します。
正常では、頻脈時に短縮、徐脈時に延長します。
正常、異常の判断には、心拍数の補正が必要です。
心拍数で補正した、**QTc(Bazettの式)**が頻用されます。
📙医療関係者むけ、お勧め書籍|Amazonで見る
正常心電図のまとめ
- 洞調律:P波が常にⅠ, Ⅱ, aVFで上向き
- 心拍数:60回/分~100回/分
- P波:幅 < 3mm、高さ < 2.5mm
- PQ(PR)間隔:3~5mm
- QRS幅:< 3mm
- QT間隔:QTc = QT÷√RR 0.36秒~0.44秒
- 平均電気軸:0°± 90°
- 異常Q波を認めない
- R波の電位:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,aVF R < 20mm、aVL R < 12mm、V5,V6 R < 26mm、SV1 + RV5 or RV6 < 40mm、RV1 < 7mm
- V1:R/S < 1
- T波:高さ < 12mm、≧その誘導のRの1/10
- 陰性T波があっても良い誘導:Ⅲ, aVL, aVF, V1, V2, (V3 女性)
- T波:Ⅰ, Ⅱ 常に陽性
- ST上昇なし:肢誘導 ≧ 1mm、胸部誘導 ≧ 2mm
- U波:高さ < 2mm
- U波:陽性
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも不安の解消や、次の一歩の参考になれば嬉しいです。
