毎年の健康診断や学校検診の心電図検査で、
「房室ブロック」と指摘を受けると
びっくりしますよね。
「症状は特にないんだけど、放置でいいの?」
「原因は何が考えられるの?」
「どんな病気?ペースメーカーが必要って聞いたことあるけど…。」
・・・と不安になったり
考えてしまいますよね。
この記事では循環器専門医が
房室ブロックの心電図について、
健康診断後の対応や、原因・症状、
所見の特徴や種類を解説していきます。
※本記事は診断や治療を目的としたものではありません。
※受診の判断材料や、理解を深める参考としてお使いください。
※検査元から受診指示がある方は、必ず医療機関をご受診ください。

本記事は、下記関連ページの続きとして、
記載いたしました。
ご興味のある方は
是非、最初から読んでみて下さいね。
房室ブロックの心電図とは|特徴、種類をザックリ解説
房室ブロックは、
異常の程度(少しゆっくり~完全にブロック)によって
以下のように分類されます:
- 1度房室ブロック
- 2度房室ブロック(Wenckebach[ウェンケバッハ型])
- 2度房室ブロック(Mobitz[モビッツ型])
- 2度房室ブロック(2:1)
- 2度房室ブロック(高度)
- 完全房室ブロック(3度)
一般的には下にいくほど
重症度が高いとされています。
房室ブロック|シンプル解説
心臓は、上側の「心房」と
下側の「心室」に分かれています。
この2つは電線のような
電気の通り道でつながっており、
電気信号が流れることで上側と下側(心房と心室)が
タイミングを合わせて収縮します。
この心房と心室をつなぐ“電線”に
異常がある状態を、
「房室ブロック」と呼びます。
症状の有無や重さは人によって異なり、
軽度で経過観察となる場合もあれば、
精密検査やペースメーカー治療が
必要になることもあります。
心電図所見、房室ブロックと自覚症状
ブロックの程度(1度・2度・3度)によって
症状の出方はさまざまです。
1度の場合はほとんど無症状ですが、
進行すると次のような自覚症状が現れることがあります:
- 脈が遅くなる(徐脈)
- 動悸(ドキドキ感)や脈の乱れ
- めまい、ふらつき
- 息切れ
- 疲れやすさ
- 失神
- 意識を失いかける感じ
3度になると、心臓のリズムが大きく乱れ、
失神や心不全の原因になることもあります。
こうした症状がある場合や、
心電図で中~重度の房室ブロックを指摘された場合には、
循環器内科・循環器科の受診
追加の精密検査が必要です。
状況によっては、ペースメーカーによる治療が
検討されることもあります。
気になる症状がある方は、
早めの受診をおすすめします。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
✅健康診断の心電図で【経過観察】や【異常なし】…でも体調不良? それって病気?
心電図、 房室ブロックで考えられる原因や病気など
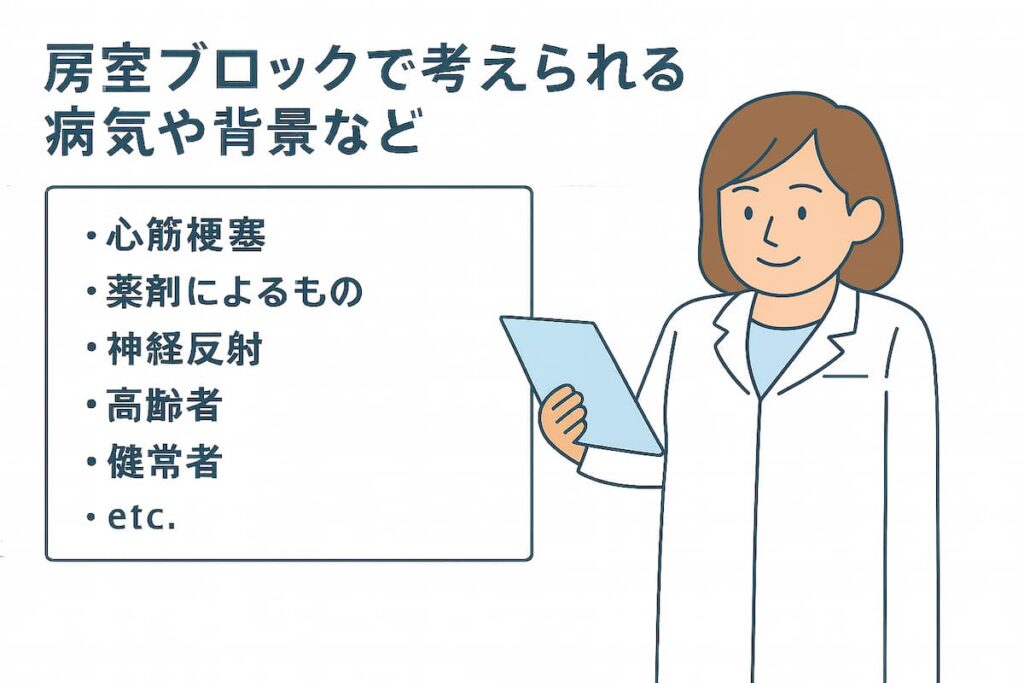
心筋梗塞
心臓を栄養している動脈(冠動脈)が
閉塞してしまう病気です。
急性期の合併症として
房室ブロックが生じる場合があります。
急性期を脱しても回復せずに、
心臓ペースメーカーが必要となる事もあります。
薬剤によるもの
脈拍をゆっくりにする作用のある
薬剤などの影響によって、
房室ブロックとなる場合があります。
薬剤の中止が検討されます。
神経反射
強い緊張や、腹痛などにより、
迷走神経の強い緊張が生じると、
房室ブロックを呈する場合があります。
高齢者
高齢者では加齢に伴い、
房室結節の機能障害が生じ、
房室ブロックとなる場合があります。
健常者
若年者やスポーツ選手に、
房室ブロックを認める事があります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図異常、房室ブロックで、クリニック受診前の確認項目
心電図検査を受けた医療機関や健康診断センターから
緊急の指示があった場合は、
まずはその指示に従ってくださいね。
それ以外の方で、
気になる症状があったり、心配な方は、
循環器内科・循環器科を標榜しているクリニックや病院への受診をお勧めします。
医師の専門分野も確認してみましょう
診療科のチェックとあわせて、
受診先の医師がどのような経歴や専門分野を持っているかを
事前に確認しておくとより安心です。
医師の専門領域が分かることで、
スムーズな診療につながる可能性が高まります。
クリニックや病院のWebサイトには、
医師のプロフィールや経歴が掲載されていることが多く
参考になります。
以下のような資格や所属があるか、
医師プロフィールでチェックしてみましょう。
- ◇◇不整脈(心電図)学会 専門医 / 認定医 / 所属
- ○○循環器学会 専門医 / 認定医 / 所属
- △△心臓病学会 専門医 / 認定医 / 所属
心臓病を得意とする
医師の診察を受けると、
追加精密検査の計画や、
治療方針のスムーズな決定が期待できます。
しかし、すべてのケースが
一つの医療機関で解決できるとは限りません。
診察や追加検査の結果によっては、
より高度な医療機器を備えた
総合病院などの専門機関への
紹介受診が必要となる場合もあります。
医師の経歴にこれらの専門資格の記載がある場合、
専門分野の病気に精通しているだけでなく、
高度医療機関(総合病院など)との連携・紹介も
スムーズに行える可能性が高いと考えられます。
事前に、一度クリニックや病院へ
電話で連絡を入れることもおすすめです。
希望する医師の診療日、予約の要・不要など確認しておくと、
当日の手続きや流れがよりスムーズになります。
とくに専門外来では、診察日が決まった曜日に
設定されている場合もあります。
事前の問い合わせで、待ち時間を短縮したり、
予約に関するトラブルを防ぐことにつながります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
心電図、房室ブロック|受診後の検査や治療への流れ
お近くの循環器内科・循環器科を標榜する
クリニックや医院への受診を考える際に、
「受診後はどんな流れになるのだろう?」
と疑問を持たれますよね。
受診後の流れについて
医師の診察のうえで、心電図の「房室ブロック」が
- 本当に心配な心電図異常か
- 様子を見るだけでいいものか
といった判断のため、
当日〜2週間程度以内に、外来で出来る追加検査が
行われるのが一般的です。
※個々の検査については、後のセクションで解説いたします。
検査結果が出た後の主なパターン
診察や検査結果に基づいて、
その後の方針が決まります。
1. 経過観察となるケース
軽いもの:
「特に問題ないでしょう。
お困りの事がありましたら、再度ご来院ください。」
念のため:
「○ヵ月後をめどに再受診いただき、
定期的に確認しましょう。」
頓服の相談:
「困った症状などが出たときのため、
必要に応じてお薬を持っておきましょう。」
万一に備えて:
「△△の症状が出たら、
救急を含めて、急いで医療機関を受診してください。」
2. お薬による治療が始まるケース
診察および諸検査の結果、医師の判断で
不整脈を整えたり、
心臓に負担を軽減するようなお薬が処方され、
定期通院が始まる場合もあります。
3. 大きな病院への紹介となるケース
さらに詳しい検査や、
お身体に一定上の負担がかかる治療が必要と
判断された場合には急性期総合病院
大学病院、専門病院などへの紹介が行われます。
緊急対応が必要なケース(まれ)
重大な心疾患や
緊急性の高い不整脈が疑われる場合は、
紹介状を持っての当日中の受診を
勧められることがあります。
※場合によっては、救急搬送となることもあります。
紹介予約による検査~治療
CT・MRI・シンチグラフィ・心臓カテーテルなど、
より高度な検査や治療が必要な場合には、
事前予約での紹介受診となります。
最初から大病院を受診しても構いませんが、
必ずしも効率的とは限りません。
総合病院は初診時に紹介状が必要であったり
専門外来の予約が取りづらく、
待ち時間や費用が多くかかることもあります。
一方で、地域のクリニックや医院では、
比較的早く診てもらえるうえ
必要な場合、大きな病院への紹介状を
書いてもらえる仕組み「病診連携」があります。
そのため、まずは初期評価を近くの医療機関で受け、
必要に応じて大きな病院などへ紹介してもらう流れが、
結果的にスムーズなケースが多いです。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
房室ブロックの心電図で考慮される追加検査
- 安静心電図検査
- 胸部レントゲン検査
- ホルター心電図検査
- 心臓超音波検査
- 血液検査
- その他
ご紹介した検査が
すべて必要になるわけではありません。
また、ここで挙げたもの以外にも、
心臓の状態を詳しく調べるための検査は多数あります。
どの検査が必要かは、
症状の有無や年齢・生活習慣・持病などの背景、
そして医師の診察結果によって異なります。
【安静心電図検査】
- 所要時間: 約1分
- 自己負担額: 約130円 ~ 400円(自己負担割合によります)
「健康診断でもやったのに、もう一度?」
と思われるかもしれません。
しかし、タイミングを変えて
再検査することで
前回との変化や再現性の有無を
確認することができます。
通常、検査当日に結果説明が可能です。
【胸部レントゲン検査】
- 所要時間: 約1分
- 自己負担額: 約130円 ~ 400円(自己負担割合によります)
胸のX線写真を撮影し、
心臓の大きさや形、肺や大血管の状態を
確認するための基本的な検査です。
心電図異常が見られた際には、
心臓以外の問題が隠れていないかを調べる
補助的な役割を果たします。
【ホルター心電図検査】
- 所要時間: 1日程度(装着時間)
- 自己負担額: 約1,750円 ~ 5,400円(自己負担割合によります)
24時間(最低8時間以上)心電図を記録する検査です。
日常生活の中で脈の変化を調べることができ、
一時的な不整脈の発見にも役立ちます。
装着中は、激しい運動や大量に汗をかく作業は
控える必要があります。
解析に時間がかかるため、
結果説明は検査機器返却後2~3日かかります。
【心臓超音波検査(心エコー)】
- 所要時間: 約20分
- 自己負担額: 約880円 ~ 2,800円(自己負担割合によります)
テレビCMなどで妊婦さんがお腹の赤ちゃんを診てもらう場面を、
見たことがあるかもしれません。
それと同じ超音波の原理を使って心臓を観察します。
左胸に探触子(プローブ)をあてて、
心臓の筋肉の状態、ポンプとしての機能
弁の動き(血流の逆流や狭窄の有無)などを
動画で確認できます。
体に害のない、安全な検査であり
当日に結果説明が可能です。
【血液検査】
- 所要時間: 約3分
- 自己負担額: 約1,200円 ~ 3,600円(自己負担割合によります)
採血によって、電解質バランスの乱れ、
心臓の負担具合、
時に薬物の血中濃度などを確認します。
これらの異常は
不整脈の原因となることがあります。
結果の出るタイミングは、
当日~1週間程度と検査内容により異なります。
▷補足
- 所要時間は、検査自体にかかる時間です(説明や待ち時間は含みません)。
- 自己負担額は検査費用の概算であり、診察料や処方薬費などは含まれていません。
- 制度改定などにより変更される可能性もあります。
- 所要時間・費用・結果説明までの期間は、医療機関ごとの体制によって異なります。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
スマートウォッチ心電図で房室ブロックはわかる?
房室ブロックの心電図では
PQ(PR)間隔の延長や、
一部の波形の抜け落ちとして現れます。
スマートウォッチ心電図では、
脈が速い・遅い、不規則であるといった
リズムの異常を検知することが可能です。
つまり「脈がゆっくりになっている」「乱れている」までは、
わかるかもしれません。
しかし、波形そのものを精密に評価する機能はなく、
房室ブロックの診断に必要なPQ(PR)間隔の延長や
波形の変化を見分けることはできません。
房室ブロックの診断には、
病院やクリニックで行う
12誘導心電図が必要です。
スマートウォッチ心電図はあくまで
「日常のリズムチェック」として活用し、
気になることがあれば
早めに循環器内科・循環器科を受診を検討しましょう。
※執筆時点での情報をもとにしています。
※スマートウォッチの機能や医療機器認定は日々アップデートされていますので、
最新情報はメーカーや公式発表をご確認ください。
房室ブロックの種類や特徴を更に詳しく解説します
ここからは、少し難しい話かもしれません。
ご興味のある方は読み進めて下さいね。
房室ブロックは
心電図リズムやつながりの異常であり
不整脈の一種です。
心臓は、右心房にある洞結節より生じた電気刺激が、
房室結節を介して心室に伝わり、収縮します。
心房から心室に伝わるはずの、
電気刺激の通りが悪かったり
切れてしまっていたりする状態を
房室ブロックと呼びます。
【1度房室ブロック】
房室伝導の速度が遅れることにより、
心電図上ではPQ(PR)間隔が延長します。
心電図検査で
PQ(PR)間隔 ≧ 0.20sec(5mm)となった場合、
1度房室ブロックと呼びます。
加齢とともにPQ(PR)間隔が
延長する事があります。
また2度房室ブロック、完全房室ブロックへ
移行する事もあります。
【2度房室ブロック(Wenckebach ウェンケバッハ)】
Wenckebach型2度房室ブロックでは、
PQ(PR)時間が次第に延長し
数拍おきにQRS波が出現しなくなり
長い休止期を示します。
休止期の間に、房室結節は回復する事が出来るため、
休止期直後PQ(PR)間隔は
その直前のPQ(PR)間隔より短くなります。
このPQ(PR)間隔の変動のため、
R-R間隔は、次第に短縮されて
長い休止期となる心電図所見を示します。
急性心筋梗塞時に生じる事が知られていますが、
一過性の場合が多いとされます。
迷走神経の強い緊張のために生じる事もあります。
比較的良性の不整脈とされています。
【2度房室ブロック(Mobitz モビッツ)】
Mobitz型2度房室ブロックでは、
PQ(PR)間隔は一定のまま、突然QRS波が出現しなくなり、
休止期となります。
休止期の前後でも
PQ(PR)間隔は一定を示します。
R-R間隔も一定で
QRS波が出現しない場合
直前のR-R間隔の2倍の休止期となります。
広範な前壁中隔梗塞例でみられることがあります。
自覚症状などによって、
しばしば心臓ペースメーカー植え込みが
必要となる場合があります。
【2度房室ブロック(2:1)】
2:1の2度房室ブロックでは
P波1拍おきに、
QRS波が出現しなくなります(房室伝導比が2:1の状態)。
そのため、PQ(PR)間隔が次第に延長するのか、
一定なのか分からず、
Wenckebach型か、Mobitz型かの
判別が困難となります。
長時間心電図を追っていくと
判別可能となる事があります。
自覚症状などによって、
しばしば心臓ペースメーカー植え込みが必要となる場合があります。
【2度房室ブロック(高度)】
P波とQRS波の割合がさらに悪化し、
3:1、4:1と進行すると
高度房室ブロックと呼ばれます。
完全房室ブロック(3度)のギリギリ手前の状態です。
心臓ペースメーカー植え込みが必要となる場合が多いです。
【完全房室ブロック(3度)】
完全房室ブロック(3度)では、
P波とQRS波が全く別々のリズムとなります。
そのため、PQ(PR)間隔は一定せず、さまざまとなります。
洞調律例では、P波は洞調律のリズム、
QRS波は房室接合部性、
または心室性の補充調律となるため
P-P間隔は一定、R-R間隔も一定となりますが、
P-P間隔とR-R間隔は全く異なった心電図を呈します。
心房細動例では、通常R-R間隔は不整となります。
心房細動であるにも関わらず
R-R間隔が長く、
一定のリズムを示す場合は、
完全房室ブロック(3度)と診断されます。
R-R間隔が一定ということは
QRS波が補充調律であることを示すからです。
完全房室ブロックでは
心臓ペースメーカー植え込みが必要となる場合が多いです。
📙医療関係者むけ、お勧め書籍|Amazonで見る
以上となります。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました!
