最近よく耳にする、
「スマートウォッチで心電図がとれる」という話題。
「それって、クリニックや病院の心電図と同じなの?」
「不整脈は本当にわかるの?」
「医療機器なの?」
・・・と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
病院やクリニックで行う12誘導心電図検査と、
スマートウォッチ心電図の違いを、
やさしく解説します。
また、医療機器として認定されている、
スマートウォッチ心電図と、
そうでないものの違いについても触れていきます。
※執筆時点での情報をもとにしています。
※スマートウォッチの機能や医療機器認定は日々アップデートされていますので、
最新情報はメーカーや公式発表をご確認ください。
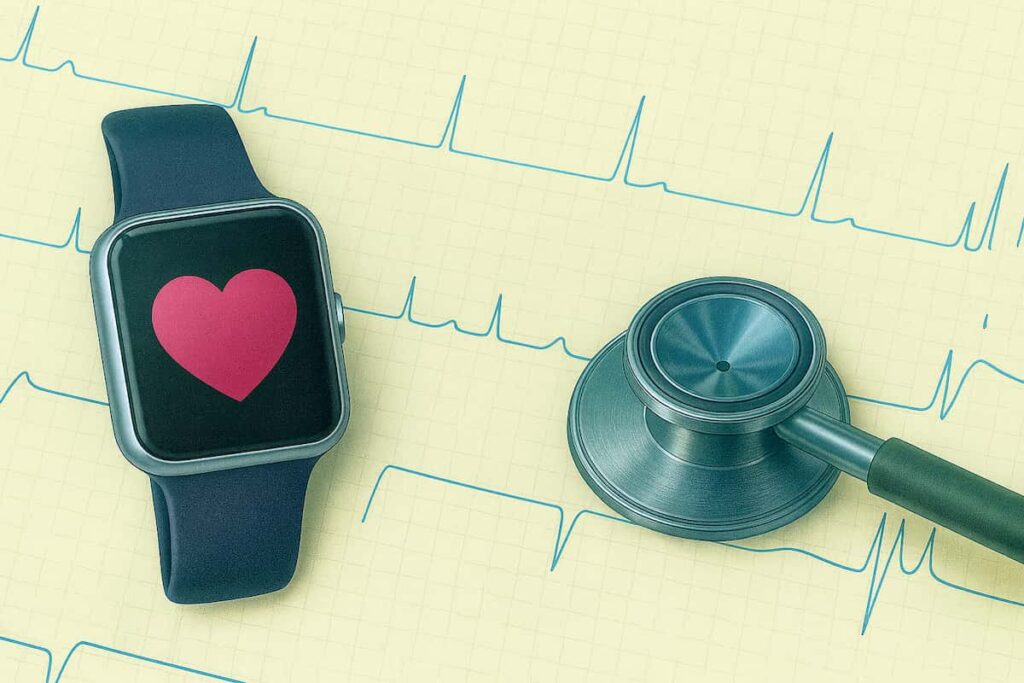
病院・クリニックで行う12誘導心電図検査とは?
病院やクリニックで行う心電図検査は、
通常、胸や手足に電極を装着して行う、
「12誘導心電図」です。
- 12方向から心臓の電気信号を記録する(👉詳しくはこちら)
- 「波形の異常」や「不整脈」など幅広く診断できる
- 心筋梗塞、心肥大、虚血性心疾患などの発見にも有効
つまり、総合的に心臓の状態を評価できる検査が、
12誘導心電図なのです。
👇お近くの循環器内科・循環器科を探す
スマートウォッチの心電図機能とは?
一方でスマートウォッチの心電図機能は、
通常、手首や指先を使った1誘導心電図です。
- 測定できるのは「不整脈の一部(とくに心房細動)」や「脈が速いか遅いか」
- 12誘導心電図のように「波形の異常」までは難しい
- ただし、日常生活の中でいつでも・繰り返し測定できるという大きな強みがある
つまり「幅広く詳しく調べる」のは、
病院やクリニックの12誘導心電図、
「日常的にチェックする」のは、
スマートウォッチ心電図、
と役割が分かれています。
✅スマートウォッチを探す|HUAWEI公式 ONLINE STORE
医療機器認定の有無にも注意
実は、スマートウォッチ心電図機能の中にも違いがあります。
厚生労働省から医療機器として認定されているもの
「管理医療機器」として正式に承認されており、
不整脈のチェックなどに使えます。
⌚心電図機能が医療機器認定を受けているスマートウォッチ|Amazonで見る
医療機器認定を受けていないもの
健康管理やフィットネス目的としての利用にとどまり、
診断には使えません。
ご購入の際は、「医療機器認定の有無」を
確認しておくと安心です。
| 12誘導心電図(医療機関で実施) | スマートウォッチ心電図 | |
|---|---|---|
| 測定方法 | 胸・手足に電極をつけて12方向から記録 | 手首や指先で1方向(1誘導)を記録 |
| わかること | 波形の異常、不整脈全般 | 不整脈の一部(主に心房細動) |
| 強み | 心臓全体を評価できる検査 | 日常生活の中で繰り返し測定できる |
| 検査時間 | 数十秒〜数分(その場の状態を確認) | いつでも・繰り返し可能 |
| 利用目的 | 診断や治療方針の決定 | 不整脈のモニタリング、受診のきっかけ作り |
| 医療機器認定 | 医療機器として必ず認定 | 医療機器認定あり/なし両方が存在 |
どう使い分ければいい?
病院・クリニックの12誘導心電図
症状がある時や健康診断で必須となります。
心臓全体の状態を詳しく調べるためには欠かせません。
スマートウォッチ心電図
動悸がある時や普段の生活の中でのモニタリングに便利です。
いつでも測定できるのも大きなメリットとなります。
つまり、スマートウォッチは「気づきのきっかけ」、
病院・クリニックの心電図は「正確な診断」という関係です。
スマートウォッチ心電図でわかる?わからない?
当サイトでは、健康診断や学校検診などで指摘される、
心電図の各異常について、
「スマートウォッチ心電図でわかるのか?」、
という観点からも解説しています。
スマートウォッチ心電図は、
一部の不整脈をチェックするのに役立ちますが、
クリニックや病院で行う12誘導心電図とは
役割が異なります。
以下に各記事のリンクをまとめましたので、
気になる項目をチェックしてみてください。
まとめ
- 病院の12誘導心電図は「波形の異常」と「不整脈」の両方がわかる検査
- スマートウォッチ心電図は「不整脈の一部」しか見つけられないが、
日常生活で測定できるメリットがある - スマートウォッチの中にも「医療機器認定あり・なし」の違いがあるので注意
「スマートウォッチで異常が出たらクリニックや病院へ行く」
「クリニックや病院受診のきっかけとしてスマートウォッチを活用する」
このようにうまく使い分けることで、
より安心して自分の心臓を守ることができます。
動悸・胸の違和感がある方や、
スマートウォッチ心電図でご心配な方は、
循環器内科・循環器科受診をおすすめします。
